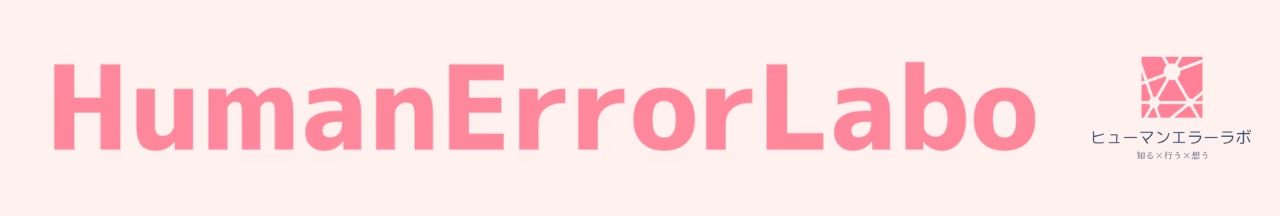「コミュニケーションエラーを考える」はXでもポストしています。その内容をこちらに転載します。
コミュニケーションエラーを考える その30
ここまでコミュニケーションエラーについて、ポストしてきましたが、ここで一区切り付けたいと思います。
人と関わりながら生活をする以上、何らかのコミュニケーションが求められます。また、コミュニケーションが発生する以上、コミュニケーションエラーが発生するリスクも出てきます。 多少のコミュニケーションエラーを起こしたとしても、多くの場合、不具合につながることはないと思います。
ただ、何も問題が起こっていないからといって、コミュニケーションエラーリスクをそのまま放置すれば、将来、大きな事故、トラブルにつながることがないとは言い切れません。
また、組織で働く場合は、チームエラーを防ぐことも必要になってきます。チーム内のコミュニケーションのあり方を随時見直して、チームで仕事することの有効性を高めることが大切ではないでしょうか。
コミュニケーションエラーを考える その29
コミュニケーションを行うのは、自分の持っている情報を他の人に提供したり、逆に情報を得るなど、単に、情報のやりとりをする目的もありますが、多くの場合は、相手に働きかけて、人間関係を構築したり、意識を変え、何らかの行動を促すことの方が多いのではないでしょうか。
人間関係を構築したり、意識を変え、行動を促すことを目的とするのであれば、目的を深掘りして、どのような状態にしたいのか、そのために、相手に何を伝えないといけないのかを検討する必要があるのではないでしょうか。
コミュニケーションエラーを考える その28
コミュニケーション要素を踏まえ、機能と行為を組み合わせたのが手段となります。
例えば、課や係などの定例会議で、単に、仕事の進捗に関する情報収集・共有の機能を主とする場合だと報告という行為が多くなります。 また、仕事の方向付けや前向きに仕事に取り組むための動機付けの場としたいのであれば、進捗状況は事前にシステムなどに入力、共有しておき、仕事上の相談を受ける時間を多くするという工夫もありではないでしょうか。
コミュニケーションエラーを考える その27
報連相もうまく活用すると、動機付けになりえます。
まず、報連相をしてくれたことにお礼、感謝の意を伝えることで、次も報連相する動機付けになります。
特に、相談は、相手の考えがまとまり切っていない内に話をされることがありますので、じっくり話を聞いて、相手の考えを整理してあげるようにすると、次も、あなたに相談しようという気持ちになるかもしれませんよ。
コミュニケーションエラーを考える その26
指示というコミュニケーション行為において、動機付けという機能を織り込むことも可能です。
例えば、ある作業・業務を指示する際に、なぜ、それが必要なのか、それを達成することで得られる成果や指示相手への期待などを含めて、説明することで、相手も、単に、作業・業務の指示を受けるよりも、前向きに仕事に取り組めることにつながりうるのではないでしょうか。
コミュニケーションエラーを考える その25
連絡はタイミングも大切です。
情報を得たら、新鮮な内に伝えることが必要になることもありますし、何かアクションをする前に伝える方が効果的なこともあります。 連絡により伝える情報を活用して、どうしたいのかという意図が重要で、その意図に合わせた連絡のタイミングがあるのではないでしょうか。
コミュニケーションエラーを考える その24
連絡は、伝える内容である情報の質が大切です。
その23では、連絡すべき情報の判断を組織内で共有することの重要性をお伝えしました。
情報の質という意味では、その情報の確からしさをしっかり確認することも重要です。単なる伝聞情報なのか、客観的証拠の裏付けがあるのかでは、受け止め方が違ってきますよね。
コミュニケーションエラーを考える その23
連絡も立派なコミュニケーションであり、チームエラーを防ぐことにもつながります。
みなさまの会社では、何を連絡すべきかを、組織やチームの中で共有されているでしょうか。
連絡すべき情報かどうかの判断を個人に委ね過ぎていると、本来、直ちに共有すべき情報が連絡されず、思わぬ問題に発展するかもしれませんよ。
コミュニケーションエラーを考える その22
その21で、相談について触れましたが、みなさまは部下や後輩から、よく相談を受けますか。
こまめに相談があれば、事前に、問題の芽に、いち早く気づくことができるかもしれませんし、早い段階で軌道修正ができるかもしれません。 報告も、もちろん重要ですが、タイミングを明確にして、必要最小限とし、相談をどう増やすかを考えてみてはいかがでしょうか。
コミュニケーションエラーを考える その21
問題が発覚してから、もしくは、問題の兆候が見えてからの報告は、報告する側が緊張するのは、その20でも触れた通りです。
可能なら、ちょっとでも、気になることや不安があったら、すぐ相談できるような雰囲気や環境を、普段から意識して作ることが大切ではないでしょうか。
例えば、ちょっとした相談をしてくれた相手に対して、感謝の意やお礼を伝えたり、更に、次、こんな状況になったら、遠慮なく、すぐ相談するように促すなど。
コミュニケーションエラーを考える その20
「部下や後輩から報告がない」という悩みをお聞きすることがあります。 その13でも触れましたが、報告は、指示を受けた人が指示を出した人へ状況などを伝えるためのものですが、報告は報連相の中で、一番、相手に緊張を強いるものではないでしょうか。特に、報告する側にとって、ありがたくない情報や状況に関する報告は尚更です。
そのような緊張を解きつつ、普段から、報告しやすい職場づくり、雰囲気づくりを作ることが大事です。
コミュニケーションエラーを考える その19
その18では、会話に触れましたが、対照的なのが対話です。 対話は、特定の目的を持ち、相互理解を深めるためのコミュニケーションです。
例えば、問題解決という目的のために、お互いの意見を交換したり、認識をすり合わせるために行われるのは対話ということになります。 この場合、認識をすり合わせたつもりが、実は合っていなかったというコミュニケーションエラーが起こるリスクがあります。
コミュニケーションエラーを考える その18
会話もコミュニケーション行為の一つです。 会話とは、特定の目的を持たず、広く浅くコミュニケーションを取ることです。
例えば、会話によって、いろいろな情報収集することで、相手のことを知り、人間関係を構築することにもつながります。 相手のことを知れば、エラーを防ぐために、どうサポートすればよいかのヒントが得られるかもしれませんね。
コミュニケーションエラーを考える その17
何か問題が発生した時に、相手から情報を聞き出すコミュニケーションを行うことが求められます。
情報収集を主目的としたインタビューと何らかの目的をもって、それに関する情報を聞き出すヒアリングでは、意図もやり方も異なってきます。 それが相手にうまく伝わっていないと、相手から必要な情報をうまく引き出せないコミュニケーションエラーが発生するかもしれません。
コミュニケーションエラーを考える その16
情報伝達が一方通行になりがちになる説明会を改善するための一つとして、例えば、受信側を少人数のグループにして、口頭の説明だけではなく、メンバーからの質問を受けるなど、意見交換できる場にするという手段もあります。
その場合、全員に説明しようとすれば、複数回実施をしないといけなくなり、今度は、各回ごとの説明内容のブレなどがコミュニケーションエラーリスクとなりえます。
コミュニケーションエラーを考える その15
コミュニケーション機能や行為を組み合わせたものが手段となります。
例えば、組織の方針を関係者に理解させる手段として、部門長(発信側)が多数のメンバー(受信側)に対し、組織方針という情報を口頭(伝達)で、方向付け(機能)のために、指示(行為)を行うという方針説明会などが考えられます。この手段だと、情報伝達が一方通行になりがちで、うまく方針の意図が伝わらないエラーが起こるかもしれません。
コミュニケーションエラーを考える その14
声かけもコミュニケーション行為になります。
例えば、表情や様子が気になる人に声かけをする場合、「私はあなたのことを見ているよ、気にしているよ」というメッセージを込めた動機付けのこともあるでしょうし、相手の困りごとに関する情報を集めるきっかけとすることもあるでしょう。
声かけ一つで、エラーリスクを察知して、事前に手を打つことができるなど、エラーを抑制することができる一方で、声かけが不足していることで、結果として、エラーが発生してしまうこともあるのではないでしょうか。
コミュニケーションエラーを考える その13
報連相もコミュニケーション行為の一つです。
指示を受けた人が指示を出した人へ状況などを伝える報告、必要、有益な情報を組織内でお互い共有しあう連絡、他の人に意見や助言を求める相談など、報連相をうまく使うことで、エラーリスクを低減したり、エラーを防ぐこともできます。
コミュニケーションエラーを考える その12
コミュニケーション機能を発揮するための具体的な行い・振る舞いとして、コミュニケーション行為があります。
あるべき姿を示したり、そこに至るために、どうすべきかを指し示すことが指示ですが、コミュニケーション行為の一つになります。指示がうまく伝わらないことで、コミュニケーションエラーが起こりえます。
コミュニケーションエラーを考える その11
動機付けもコミュニケーション機能の一つです。
動機付けを行うことで、相手のパフォーマンスを維持したり、効果的に行えば、パフォーマンス向上になることもあります。
一方、動機付けが機能しないと、パフォーマンスが下がり、ヒューマンエラーにつながることもありえます。
コミュニケーションエラーを考える その10
情報収集・共有もコミュニケーション機能の一つです。
単に、情報収集だけであればエラーリスクは少ないかもしれませんが、情報共有は、(情報)発信側の意図が(情報)受信側に、うまく伝わらないエラーリスクがあります。
コミュニケーションエラーを考える その9
コミュニケーション機能の例としては、方向付けがあります。
方向付けとは、あるべき姿を示し、その実現のために必要な指示を行うことです。
この方向付けがうまくいかないと、発信側の意図に沿った対応を受信側がしてくれない可能性があり、エラーとなりえます。
コミュニケーションエラーを考える その8
(情報)発信側が(情報)受信側に、どのようなコミュニケーション上の働きかけをするかという視点で考えると、コミュニケーション機能にも着目すべきです。
コミュニケーションエラーを考える その7
例えば、(情報)発信側が1人、(情報)受信側が多数、言葉だけの情報で、一方向の口頭での伝達だと、受信側の認識がそれぞれ微妙に違い、発信側の伝えたい意図が伝わらず、コミュニケーションエラーが起こりえます。
※その1~6までは、「コミュニケーションエラーを考える」の内容を細分化して、お伝えしておりますので、そちらをご覧ください。