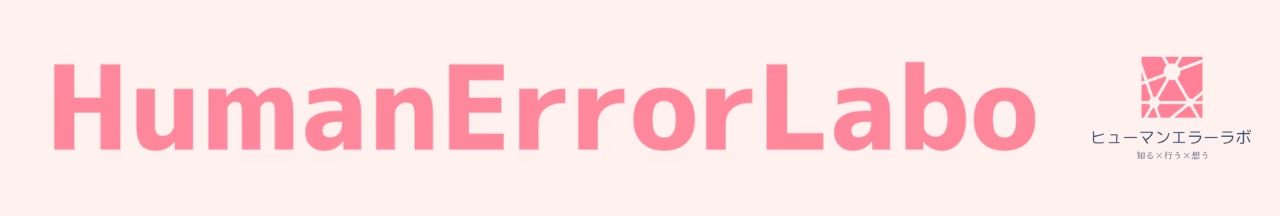ヒューマンエラーに起因する問題は、ある個人が起こすエラーから始まりますが、多くの仕事がチームで行われる以上、チームの問題とも言えるのではないでしょうか。その意味では、チームでいかにヒューマンエラーを防止するかという発想が重要になります。当ラボでは、チームで行われる仕事で発生するヒューマンエラーをチームエラーとします。また、ここで、チームといっているのは、組織上の部門や部署に限らず、ある仕事をする際、複数人で仕事を分担して行っている場合に、その複数人のひとかたまりのことだとお考えください。
チームエラー発生のメカニズム
まず、チームエラー発生のメカニズムを考えてみましょう。
チームで仕事をしているとはいえ、仕事を個人ごとに分担して行う以上、最初は、ある個人のヒューマンエラーから始まります。個人の範囲内で、自分の間違いに気付き、何らかの対処をすればチームエラーにはなりません。この段階で、エラーを防ぐことが出来たら、チームエラーの元になる個人のエラーの発生を抑えることになりますから、発生防止と言えます。この段階で防止できることが理想的であり、当ブログの他のページでも、いろいろな角度から、ヒューマンエラーのタイプや発生メカニズム、エラー要因、対策の視点などに触れておりますので、是非、「記事・事例のまとめ」も参照ください。
しかしながら、常に、個人の範囲でエラーを防げるとは限りません。そうなると、チームでエラーを防止することが重要になってきます。つまり、仮に、個人のヒューマンエラーが発生して、それを防止できなかったとしても、チームでエラーを組織外に流出させず、不具合を発生させない、いわゆる、流出防止が求められることになろうかと思います。
まとめると、
・ある個人のヒューマンエラーが発生する。
・そのエラーに手が打たれていない状態で、チームの他の人に仕事が渡される。
・チーム内でも、エラーに防止し切れずにチーム外に流出し、不具合が発生する。
というメカニズムでチームエラーが発生すると言えるのではないでしょうか。
チームでエラーが流出するメカニズム
更に、チームでエラーが流出する、つまり、流出防止ができないメカニズムを掘り下げてみましょう。当ラボでは、チームでエラーが流出する流れを以下のように整理しています。
| 見つけられない | チームでエラーに気づかない、見つけられない。 (例)エラーを見逃す。 |
| 指摘されない | (見つけても)エラーを放置する、指摘しない。 (例)後で指摘しようとして忘れてしまう。 |
| 指示されない | (指摘はしたが)エラーへの対処を指示しなかったり、エラーの対処を適切に指示できない。 (例)自分が指示する役割ではないと判断した。 |
| 伝わらない | (指示はしたが)指示がうまく伝わらない。 (例)指示する人が言い洩らす。指示を受ける人が聞き間違える。 |
| 対処されない | (指示は伝わったが)指示通り対処されない。 (例)対処する人が方法・手順を間違える。 |
チームで仕事をする、エラーを防止するといっても、それを行うのは人間ですから、上記のようなリスクがあり、チームでエラーを防ごうと思えば、このようなリスクを減らすための方策が必要になります。
参考までに、以下の動画に出てくる図では、分かりやすさを重視して、チームが1つのようになっていますが、現実には、チームの層が何重にもなることは当然ありえます。
最後に
チームで仕事する以上、チームのメンバーがコミュニケーションを取りながら仕事をすると思いますので、チームエラーの背景にはコミュニケーションの問題も存在しうるのではないでしょうか。コミュニケーションのとらえ方やコミュニケーションエラーに関しては、「コミュニケーションエラーを考える」も参照ください。
また、Xでも、チームエラーに関してポストしております。上記内容を踏まえたプラスアルファの内容を抜粋して、当ブログ上でも閲覧できるようにしておりますので、「チームエラーを考える Xでのポスト」も是非ご覧ください。