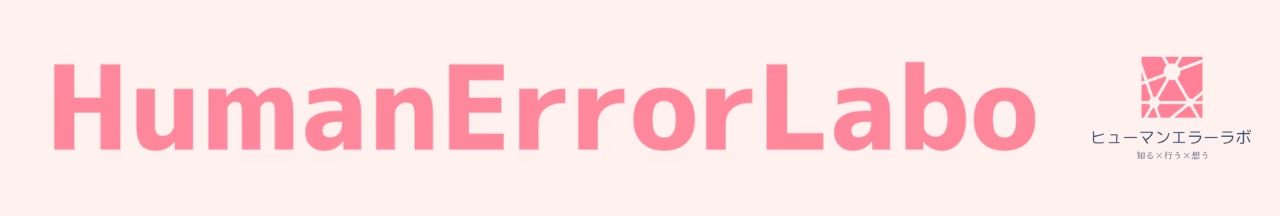とある新聞社で誤報があったようです。
国会議員が採用していた公設秘書2人について、東京地検の強制捜査などが近日中に行われるという報道に関して、対象を取り違えたとのことです。

この事象をヒューマンエラー視点で考えてみたいと思います。
取材~報道までのプロセス
まず、着目すべきことは、情報を聞き込んでから、記事として公開する報道のプロセスだと思います。
(聞き込んだ)情報⇒(一記者としての)取材結果まとめ⇒(新聞社としての)報道記事
というように、とある情報が新聞社として報道する記事となるまでに、いろいろなプロセスがあり、そのプロセスのどこかで強制捜査対象の取り違いが発生したとのことですから、まず、取材~報道までのプロセスを分解してみていく必要があります。
当方は、新聞社に勤務したことがないので、以下はあくまでも想定です。
①情報の聞き込み
②情報の裏取り
③取材結果のまとめ・執筆
④記事の公開・報道
と、こんな感じでしょうか。
取材~報道プロセスにおけるヒューマンエラーリスク
取材~報道プロセスにおけるヒューマンエラーリスクを抽出してみたいと思います。
| 取材~報道プロセス | ヒューマンエラーリスク |
| ①情報の聞き込み | ①-1【認知エラー】取材元の発言の聞き間違い (例)強制捜査対象者やそれを特定する情報の聞き間違い ①-2【認知エラー】聞き取った情報の認識間違い (例)聞き取った情報があいまいで、記者が勘違いをした。 |
| ②情報の裏取り | ②-1【記憶エラー】後で裏取りしようと思い、その後、すっかり忘れてしまった。 ②-2【判断エラー】情報を裏取りは必要ないと判断した(結果的に裏取りがされなかった)。 ②-3【判断エラー】裏取りは必要だと思ったが、早く報道しようとして、裏取りを省こうと判断した。 (例)他社に先駆けて、いち早くスクープしようとして、裏取りを省く判断をした。 ②-4【認知エラー】裏取りはしたが、そこで得た情報を聞き逃した、聞き間違えた、認識を間違えた。 |
| ③取材結果のまとめ・執筆 | ③-1【行動エラー】執筆の際に、文字を打ち間違えた。 (例)取材を同時並行で進めていて、別の取材対象の人名を間違えて打った。 ③-2【認知エラー】(人名を打ち間違えていたとして)確認、チェックの際に、人名の間違いを見逃した。 |
| ④記事の公開・報道 | ④-1【認知エラー】(人名を打ち間違えていたとして)記事公開前の確認、チェックの際に、人名の間違いを見逃した。 ④-2【判断エラー】記事公開前に、記事執筆者以外の第三者の視点で裏取りが必要にも関わらず、本件記事は必要ないと判断した(結果的に裏取りがされなかった)。 |
細かい状況が分からないので、多分に想定が入っていること、ヒューマンエラーリスクを抽出する視点をご理解いただく例として挙げてみたので、他にもヒューマンエラーリスクがありうることはご容赦ください。
仕事に置き換えると
この事例を取り上げてみたのは、新聞社の誤報を断じたいからではありません。
私たちが仕事をする上で、似たようなことが起こりうると考えるからです。例えば、
・営業活動で、とある情報を聞き込んできて、その情報に基づき、お客さまへの提案を作成したが、提案の骨子となる重要な事実に対する認識がずれていた。
・社内で事故が起こり、まず、現状把握をしたが、事故発生の背景に関する事実の認識が間違えていた。
・お客さまからクレームを受けて、報告書を作成、提出したが、お客さまから記載内容が事実に沿っていないと指摘された。
など、間違えた情報に基づき、業務を進めてしまい、その結果、対応、事後処理に追われることは、日常の仕事でも十分ありえると思います。
新聞社は、報道の影響の大きさから、本ブログの「事実って何?」でも触れましたように、情報の確からしさを踏まえて、事実の認定には相当慎重に、かつ、重視して実施していると思います。そのような組織でも、このような事態が発生しうるということがヒューマンエラーの本質を表しているのではないでしょうか。
しくみという観点でみると、「スイスチーズモデル」が重要なことを示唆していると思います。詳細は以下の動画をご覧頂きたいですが、要するに、
「ヒューマンエラーに起因する事故・トラブルは、何重にも仕掛けられた歯止めのしくみのほころびや隙をついて発生する」
ということです。
つまり、完璧なしくみはないと思って仕事をしないと、思わぬ所で大きな事故・トラブルに見舞われるかもしれないことを改めて認識しないといけないのではないでしょうか。以下の記事もよろしければご覧ください。

また、チームエラーという観点でも気になります。
誤報のきっかけとなったのは、取材した記者のヒューマンエラーだったのかもしれませんが、新聞社として、記事を公表する以上、組織、チームとして、ヒューマンエラーを防ぐしくみがどこまで機能したのかも今後、検証されると思います。

その意味では、もちろん、記者個々の誤報につながるヒューマンエラーをどう防ぐかも重要ですが、記者も人間ですから、間違えることはあります。それを踏まえた上で、
・組織、チームとして、ヒューマンエラーを防ぐしくみにはどのようなものがあり、どの部分がうまく機能しなかったのか。
・とはいえ、完璧なしくみがない以上、現状のしくみのどこに、「スイスチーズモデル」でいうところのほころびや隙があるのかをどう認識し、対処していたのか。
・上記のしくみのほころびや隙を踏まえた上で、どのようなヒューマンエラーリスクが残存しているのかを組織、チームで認識し合い、どう対処しようとしていたのか。
ということも重要だと思いますし、このような視点から、自社の業務プロセスやしくみの構築、運用を考える必要があるのではないでしょうか。
最後に、あくまでも当ラボの想定に基づく見解ですが、特に、情報の裏取りや事実確認に関するしくみが、記者個人だけでなく、新聞社という組織、チームとして、どのように構築、運用されていたのかがポイントではないでしょうか。例えば、
・記者個人がとある情報を事実だと認識した過程、プロセスやそのしくみ
・更に、そのプロセスやしくみを、記者個人以外の第三者(必要であれば複数)が検証できるプロセスやそのしくみ
・情報の裏取りや事実確認の重要性がどこまで、組織、チームで浸透していたのか、また、今回のような問題にならないまでも、そのリスクを感知、認識した時の組織、チームとしての対応(自社の問題だけではなく、他社の事例からも学ぶ、教訓を得る姿勢、行為も含めて)
というあたりが気になります。
みなさまは、どのように考えられますか。