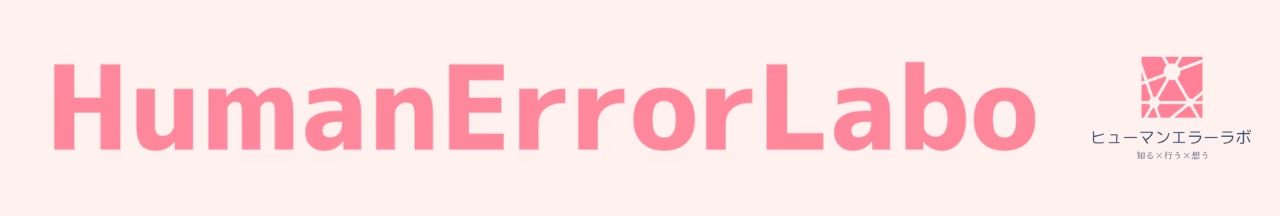チームや職場、会社の中(組織内)で発生した様々な課題に対する判断に関して、ヒューマンエラー的に見てみたいと思います。
まず、課題を認知したら、以下のような過程を経て、判断されると考えてみませんか。
(この過程は、基本的に、個人の判断でも同じです)
| 1 | 状況理解 | ①現状や課題に関する状況・状態、事象(事実と現象)、経緯に関する把握 ②あるべき姿、目的、目標(マイルストーン:中間目標含む)やゴール、また、それに至るまでの方針、計画、ステップ、進め方など、また、それらと①との比較 ③成り行きや今後の動向の見通し |
| 2 | 意思決定 | ①今、置かれている状況の解釈 ②状況の評価(緊急性/重大性など) ③対応の方向付け |
解決すべき課題として、例えば、パワハラに関するトラブルがあるとしたら、このような流れになるのではないかと思います。
| 1 | 状況理解 | ①パワハラが疑われる事案(今後はパワハラ事案とする)が発生した状況・状態を事実や現象でとらえ、その発生の経緯を把握する。 ②当該組織では、なぜ、パワハラを無くしたいのか、パワハラがない職場の状態や目指す姿、それを実現するためにどうしていくべきか(ガイドラインなど)から見ると、①で把握した内容はどう外れているのかを把握する。 ③このパワハラ事案をそのまま放置したら、どうなりそうかを見通す。 |
| 2 | 意思決定 | ①昨今の状況(世の中の動向など)を踏まえ、このパワハラ事案はパワハラに該当するのかどうか、その可能性があるのかなどを考える。 ②状況理解やその解釈を踏まえ、当該パワハラ事案は、緊急性や重大性などの観点からみてどうかを評価する。 ③②の評価結果から、対応するのかしないのか、対応するのであれば、どのように対応するのかを決める。 |
・悪意を持って、故意にトラブルを隠蔽しようとすれば、ヒューマンエラーの範疇を超える。
・トラブルの放置や不十分な対応のリスクは認識しているが、何とかなるだろう、大丈夫だろうと思って、決まり事を守らなかったり、リスクのあることをあえて行えば、あえて型エラー。
・それ以外の、上記の判断メカニズム(1状況理解、2意思決定)の中のどこかで間違ってしまったのが判断エラー。
というのが、当ラボの基本的な定義ですが、判断は人の頭の中の働きですから、その事象を特定するのは難しい側面もあります。そのため、想定されるリスクはすべて排除せずに考えるべき、つまり、例えば、あえて型エラー、判断エラーのリスクが両方とも捨てきれないのであれば、両方の可能性を検討するべきだと考えます。