ニュースを見ていたら、ある法律事務所の罰金制度に関する報道が気になりました。
報道内容
詳細は、以下を参照ください。
:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/GQRAKGJBMJJQHOIR4ZXHVB5TM4.jpg)
内容をまとめると、
・自身が所長を務める法律事務所で、罰金制度を設けていた。罰金の内容は、
提出書面の誤字脱字(1文字につき500円)
書面の重大な誤り(2万円)
依頼者へのメール送信時の男性弁護士のBCC・CC漏れ(5千円)
依頼者からの厳しいクレーム(5万円)
遅刻(5分ごとに2千円)
電話の居留守(5千円)-など。
・部下は制度が導入された令和3年6月からの約半年間で、給与を大きく上回る656万円超を支払った。
・男性弁護士は大阪弁護士会の調査に対し、罰金制度は勤務態度を改善させるためで、部下も了承し、自発的に申告していたと主張。
・罰金は事務所を退所する際に餞別(せんべつ)として返還するつもりだったと弁明。部下が懲戒請求を行った後の昨年11月に返金したという。
・同会は罰金制度を運用する中で、教育的な指導を継続していた形跡がうかがえないと指摘。パワーハラスメントとの評価は免れず、「弁護士としての品位を失うべき非行」にあたると結論付けた。
罰金の対象をヒューマンエラー的に見ると
当ラボは、ヒューマンエラーを研究していますので、まず、罰金の対象となっている項目に関して、考察をしてみたいと思います。
①提出書面の誤字脱字
パソコンで書面を作成していることがほとんどだと想定すると、キーの押し間違い(行動エラー)や、例えば、「専門」の漢字を「専問」と勘違い(判断エラー)して入力などがありえます。また、別の書類を見て、そこに書かれている文字を見間違えて、そのまま入力したのであれば、認知エラーの可能性もあります。どちらにしても、誰でも起こしうるエラーです。
②書面の重大な誤り
これに関しては、あらゆるエラーが想定されますが、具体的な内容がないので、これ以上、深掘りはできません。ただ、①の間違いが結果として、重大な誤りとされたこともあったのでしょうか。
③依頼者へのメール送信時の男性弁護士のBCC・CC漏れ
BCC・CCに、男性弁護士のメールアドレスを入れ漏らしたということだと思われますので、行動エラーです。ちなみに、「メールアドレスの入れ忘れ」と考えて、記憶エラーではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、おそらく、例えば、メール送信が10件あるとして、その内の1件、メールアドレスを入れ漏らしたということではないかと想定されますので、その場合は、行動エラーと考えるべきです。詳細は、「100個の内、1個だけ取説を入れ忘れたのは」もご覧ください。これも、誰もが起こしうるエラーです。
④依頼者からの厳しいクレーム
これも、詳細の内容が分からないので、あらゆるエラーの可能性が考えられます。これも、もしかすると、②③の結果、依頼者からクレームがあって、それが該当するとされたのかもしれません。
⑤遅刻
これも、あらゆるエラーの可能性が考えられますが、一般的には、約束の時間を忘れていた(記憶エラー)、(メールなどの)約束の時間を見逃した、見間違えた(認知エラー)という現象でしょうか。これも、あまりよろしくないことではありますが、誰もが起こしうるエラーです。
⑥電話の居留守
これも、詳細がよく分からないのですが、おそらく、男性弁護士から部下に電話を掛けた際に、その電話に出なかったことを差しているのでしょうか。家の電話の場合、外出していれば、当然、電話に出られませんし、スマホでも、仕事中や依頼者との打ち合わせ中、電車の中など、電話に出にくい状況もあったのではないでしょうか。その場合は、もはや、エラーではないですね。何をもって、居留守を判断したのでしょうか。男性弁護士側で、勝手に居留守とした可能性も否定できません。
罰金に関して
当ラボでは、このような、ヒューマンエラー防止の策としての罰金を、いかがなものかと思っています。ついつい・うっかり型エラーで、しかも、誰もが起こしうるエラーに関して、罰金を取るのは賛成できません。
いい例えかどうか分かりませんが・・・昔、日本のプロ野球で、罰金があったという話を聞いたことがあります。その罰金の対象が、守備でのエラー(野球用語のエラーです)やピッチャーの失投、バッターの見逃し三振など、本人はやろうと思っていない、しかし、誰もが起こしうるエラーに罰金が課されたらどうでしょうか。
報道によると、罰金の対象は、上記6項目を含め、全部で18項目あったようです。報道サイドが、どのような意図で、全18項目の内、上記6項目を選定したのかは分かりませんが、この6項目を見た感じでは、ついつい・うっかり型エラーで、しかも、誰もが起こしうるエラーが多く含まれている可能性があり、やり過ぎの感は否めないですね(報道サイドも、それを伝えたいがために、この6項目を選定している可能性もありますが)。
また、②書面の重大な誤り④依頼者からの厳しいクレーム⑥電話の居留守のように、基準を明確にしにくく、しくみを恣意的に運用できる可能性の高いものが含まれているのも問題ではないでしょうか。それとも、法律事務所の罰金制度なので、恣意的に運用できないように、しっかりとした基準・ルールでも決めていたのでしょうかね。
報道によると、「約半年間で、給与を大きく上回る656万円超」の罰金になったそうですが、上記6項目の罰金と照らし合わしても、異常な額に思えます。例えば、各罰金を単純計算して、どのくらいで656万円に達するかを見ると、
①提出書面の誤字脱字(1文字につき500円) 13,120文字
④依頼者からの厳しいクレーム(5万円) 約131件
⑤遅刻(5分ごとに2千円) 3280分
になります。この数値から推察すると、例えば、ある文書を作成したら、①提出書面の誤字脱字があり、それが②書面の重大な誤りとなり、そのまま、依頼者に提出したら、④依頼者からの厳しいクレームがあったので、重複して、罰金を徴収したということがあったり、②書面の重大な誤り④依頼者からの厳しいクレームのハードルが下げられるなど、恣意的な運用でもないと、こんな罰金の総額にならないと思うのは私だけでしょうか。
更に、これは、他のしくみでもありがちなことですが、おそらく、最初は、間違いを減らしたいという目的のために、その意識付けとして、罰金という手段を設けたのではないでしょうか。ところがいつの間にか、当初の目的が忘れ去られ、罰金が運用されていった可能性もあるように思います。
報道でも、「罰金制度は勤務態度を改善させるためで、部下も了承し、自発的に申告していた」とあるように、最初は、お互い、目的が共有され、部下も了承したのかもしれません。しかし、「教育的な指導を継続していた形跡がうかがえない」ともあるように、本当であれば、間違いを減らすために、適切な教育や指導をしないといけなかったにも関わらず、それがなされず、手段の罰金だけが運用された、いわば、しくみが形骸化する典型例ではないでしょうか。罰金の徴収額が増えていく中で、「何のための罰金だったのだろうか」「この罰金が間違いを減らすことにつながっているのか」と疑問を持って、途中で、立ち止まることも出来たように思います。
いずれにしても、一般的な組織のあり方として、パワハラという評価を免れない、しかも、法律事務所という、基準・ルールの代表のような法律を、厳密に運用することが求められる組織で起こったこととしては、見過ごせないことでしょうね。
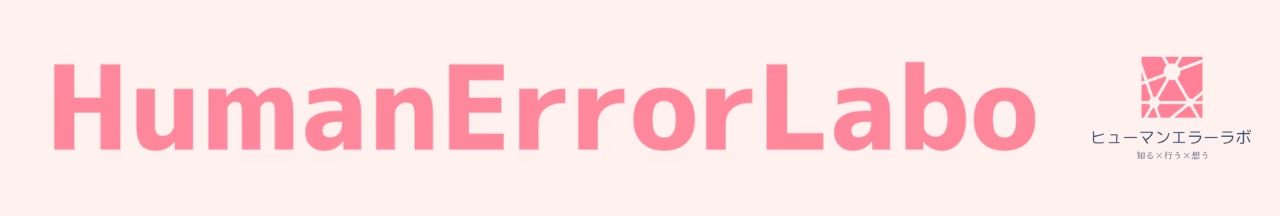



コメント