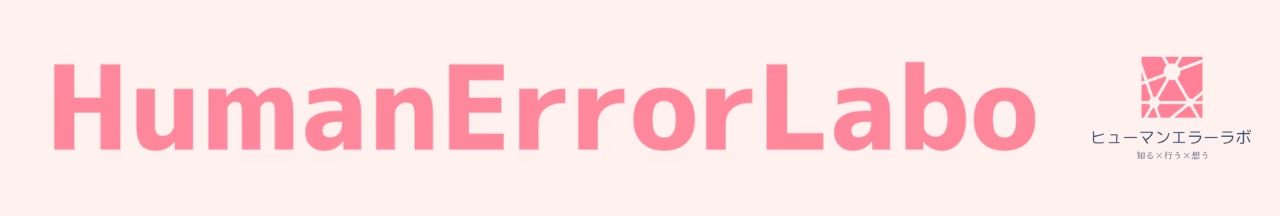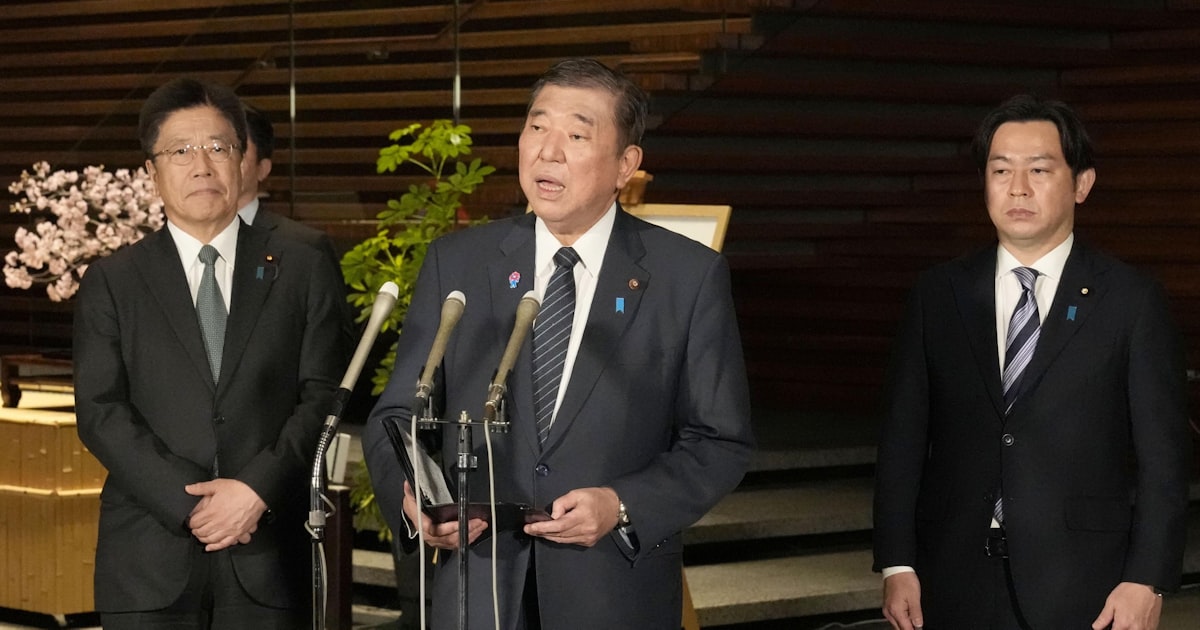
高額療養費制度の自己負担上限の引き上げをいったん見送ることを決めたようですね。
方向性が二転三転した感は否めないですね。経緯は上記の日経新聞の記事などを参照頂くとして、この記事の情報を元に、ヒューマンエラー的に見てみたいと思います。
※日経新聞の記事を元にした当ラボの想定による考察であることをご承知おきください。
厚生労働省も政府も、国会に法案を通すのが仕事ですし、他の組織でのチームエラーなどの参考になるかもしれませんので、このカテゴリーとしました。
チームエラー的に見ると
まず、前提として、
・厚生労働省としては、高額療養費制度の見直しを今国会で通すことを目標としていた。
・その目標を実現するために、こうやれば、国会を通せると想定して動いていたが、結果として、そこから外れたことになってしまった。
ということが起こっていたとします(あくまでも当ラボの想定です)。
当ラボでは、ヒューマンエラーを「目標を実現するために想定された行為」から外れた行為と定義していますので、当該制度の見直しを今国会で通すことを想定して、こうしようと思っていたことから外れたと解釈して、エラーとします。
ここで、当該制度の見直しを国会に通すために、厚生労働省と政府は同じ方向を目指して連携していく立場として、同じチームだと考えてみたいと思います。
まず、厚生労働省が、当該制度の見直しを今国会に通そうとしたことをエラーリスクとすると、その提案を受けた政府は、そのエラーリスクを見つけられたのか、もしくは、見つけられたとして、そのエラーを指摘したのでしょうか。
上記日経新聞の記事によると、厚生労働省の幹部は「患者団体は引き上げの凍結を求めていない」という見方を首相官邸に報告したそうで、首相自体も、患者団体も納得するとみていた節があるようです。このことから考えると、エラーリスクに気づいていなかったことが想定されます。もし、気づいていたなら、患者団体の意見を聞くなどの指示をした可能性はありますよね。ただ、政府から厚生労働省へ、そういう指示をしたが、それがうまく伝わらなかったか、対処されなかった可能性を否定はできませんが、上記記事では、特に触れられていないようですので、一旦置いておきます。詳細は、チームエラーを考える も参照ください。
組織内での課題に対する判断をヒューマンエラー的に見ると
次に、政府という組織で、高額療養費制度の見直しを今国会で通すという課題に対する判断をヒューマンエラーという視点でみてみたいと思います。
判断のメカニズムの詳細は、組織内での課題に対する判断をヒューマンエラー的に見るも参照ください。
政府としては、高齢化や革新的医療の広がりで医療費が膨らむ見通しの元、能力に応じて負担を増やして、当該制度の持続性を高めるようとすることを目的としており、浮いた予算を少子化対策の財源に充てる方針だったそうです。
当該制度を今国会で通せると判断したのは、以下のようなことがあったのかもしれませんね(これも、あくまでも当ラボの想定です)。
| 1 | 状況 理解 | ①(厚生労働省の幹部の話によると)患者団体は引き上げの凍結を求めていない。 ②今国会中に当該制度の見直しに関する法案を成立させるというゴールからすると、患者団体の意見を聞いた上での調整をしていると、時間が足りなくなる可能性がある。 ③野党が一部反対するかもしれないが、患者団体や与党からは特に大きな反対は出ないだろう。 |
| 2 | 意思 決定 | ①この状況であれば、このまま、国会を通せる。 ②法案を通すのに時間が掛かると、注目が集まってしまう可能性があり、スピードが最優先だ。 ③このまま、早く国会を通そう。 |
上記はあくまでも当ラボの想定ですが、上記日経新聞の記事では、野党からの反対はもちろんのこと、がんや難病患者らの反発、更に、夏に参院選を控える参院自民党や公明党からも異論が出て、今回の事態になったようです。
この記事からすると、状況理解に問題があったのかもしれませんね。高額療養費制度は、誰しもが利用する可能性のある制度ですし、元々、患者の医療費の自己負担を軽減するねらいのものなのに、その上限の引き上げるというのは、もう少し丁寧な議論が必要な課題だと思いますが、いかがでしょうか。