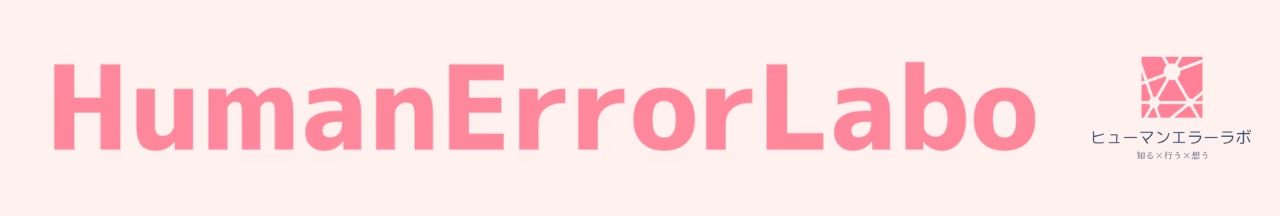日本語は難しいですね。「入れ忘れた」というと記憶エラーとも思えますが、動画の解説でもありますように、99個は取説を入れているので、取説を入れる作業自体を忘れている訳ではありません。
このケースは、行動エラーの中の「手順の抜け、漏れ」と考えるべきです。
更にいうなら、仕事柄、このような職場で、「取説を入れ忘れるな!」という注意喚起の表示を見ることがあるのですが、このケースのような行動エラーには大きな効果は期待できません。なぜなら、
・「取説を入れ忘れるな!」という表示は、取説を入れる作業そのものを忘れてしまう記憶エラーへの対策である。
・「取説を入れる」作業は、普段からその作業をしており、慣れている人からすれば、いちいち意識しなくても体が自然に反応してできる作業になっているために、1個や2個、取説を入れなくても気づかない、覚えていないことがありうる。
ということが考えられるからです。
人は完璧ではないので、何らかの理由で、1個や2個、取説を入れ漏れることはありえます。しかも、いちいち意識せずに自動的、反射的に取説を入れる作業が出来る状態にあれば、取説を入れる作業が1個や2個漏れても、気づかない、覚えていなくても不思議ではありません。逆にいうと、職場に新しく配属された新人さんは、最初は、取説を入れ漏れてはいけないと意識して作業するので、その状態では漏れることは少ないと思います。
通常、作業教育・訓練は、習得すべき作業を、いちいち意識しなくても体が自然に反応してできるようになるために行っているはずです。つまり、それは、意識しなくても自動的、反射的に体が動くくらい、そのスキルが習慣化され、身に付いている状態になっていることになります。このような状態では、何らかの異変が起こり、1個や2個漏れても気づかない、覚えていないという現象が起こりうるのです。これは、慣れている作業がゆえに起こりうるリスクとして、ある意味、スイスチーズモデルでいうチーズの穴と言えるのかもしれませんね。
ということから、「取説を入れ忘れるな!」という注意喚起の表示は無意味ではありませんが、入れ漏れるという現象そのものを防ぐことにはなりませんので、大きな効果は期待できないということです。ただし、注意喚起としての意味はありますので、意識付けとしての効果はあると考えてよいのではないでしょうか。
では、どうすればよいのでしょうか。「入れ漏れる」ことを漏らさないということは難しい、つまり、入れ漏れる要因を追究し、要因を無くしたり、減らしたりする対策(対策の4つの視点の内、2.要因対策)は難しいと考えた方がよいです。あるとすれば、作業中に声を掛けることで、作業者の注意が逸れた、阻害されたという要因を防ぐために、作業者が作業中には声を掛けないなどでしょうか。機械化、自動化する(1.全体対策)が出来ればよいですが、それが難しければ、3.ヒューマンエラー対策の内、エラーを見つけ出せる対策を考えるべきです。
例えば、100個単位で梱包するなら、作業前に、取説を100枚単位で束ね、梱包し終わった後、取説が余っていないかを確認することで入れ漏れが検出できます。これを100個単位で行うと、仮に入れ漏れが発生した場合に対応が大変なので、10個単位で行うなど最小単位で作業、確認することが大切だと思います。実際、医薬業界では、添付文書といって、医薬品の適正な使用方法や安全性に関する様々な情報が書かれたものがあるのですが、これが入れ漏れると大変なことになるので、上記のような対策を取っているようです。
100個の内、1個だけ取説を入れ忘れたのは
 ヒューマンエラークイズ
ヒューマンエラークイズこの記事は約3分で読めます。