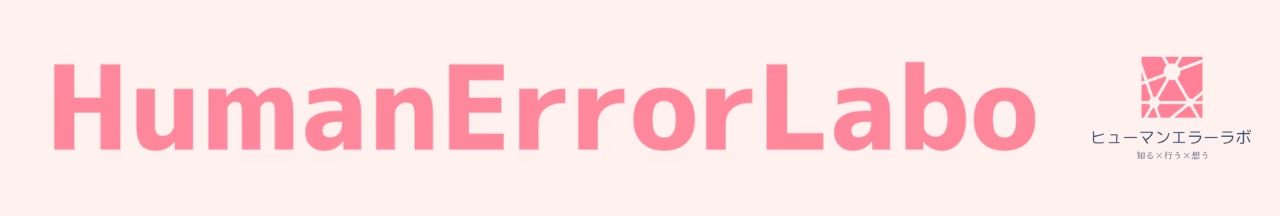当ラボでは、ヒューマンエラーにはタイプがあると考えています。
それに関して、触れてみたいと思います。
一般的なタイプ分類
一般的なタイプ分類としては、「2分類」「3分類」があります。
| 2分類 | 内容 |
| コミッション エラー | 実行すべきではないことをするエラー 〇〇するべきところを、××(〇〇と別のこと)をしてしまった。 |
| オミッション エラー | 実行すべきことをしないエラー 〇〇するべきところをしなかった、やり忘れた。 |
| 3分類 | 内容 |
| スリップ | 目的(やろうとしていること)は正しかったが、行為段階での誤り |
| ラプス | 短期な記憶の喪失 |
| ミステイク | 行為は完全に計画通り実施されるかもしれないが、計画自体が望ましい目標を達成するには不適切 |
みなさまもネットなどで、例えば、「ヒューマンエラーの分類」というキーワードで検索して頂くと上記内容に行き当たると思います。
私も完璧に調べた訳ではありませんが、その根拠になっているのは、以下の書籍だと考えています。そうでなかったとしても、ヒューマンエラーを理解する上では、非常に良い書籍だと思いますので、興味のある方は、是非お読みください。私も大いに参考にさせて頂いております。
保守事故: ヒュ-マンエラ-の未然防止のマネジメント www.amazon.co.jp
当ラボが考えた、ヒューマンエラー技術化の切り口
私は、15年以上前に、ヒューマンエラーに興味を持ち、コンサルティング、研修・セミナーなどを行えるように、技術化を目指しました。当時、上記書籍を含めて、ヒューマンエラーに関して触れられている書籍を出来る限り、かき集めて、目を通しました。その中で、ヒューマンエラーの技術化を図るに当たって、以下がポイントになると感じていました。
(1)ヒューマンエラーの未然防止につながる切り口、視点が必要である。
(2)ヒューマンエラーがなぜ発生するのか(発生メカニズム)を分かりやすくどう伝えるか、更に、その発生メカニズムを踏まえたエラー要因抽出視点を整理する。
(1)に関して、事故やトラブルが発生していなくても、作業・業務を現場で実際に観察したり、現場で観察せずとも、作業標準書、手順書を見るなど、作業・業務をイメージして、エラーリスクを抽出できる切り口、視点が必要であり、エラーのタイプがそれにあたると考えました。
(2)に関して、エラーのタイプがあるということは、タイプごとにエラー発生メカニズムも違ってくる、更に、エラー発生メカニズムが異なれば、エラー要因も変わってくる、そのエラー要因を抽出するためのチェックリストが作成できないかと考えました。
その当時、いろいろな書籍を拝見したのですが、ヒューマンエラーやその発生メカニズムを、体系的に、分かりやすく解説したものはない(上記で紹介した「保守事故」は内容自体は分かりやすいのですが、(1)の視点で考えると、ちょっと複雑かも)という印象を持ちました。そこで、自分で整理してみようとなった訳です。
(2)のエラー発生メカニズムやエラー要因チェックリストは、当ラボの考えるヒューマンエラー技術の核となる部分ですので、コンサルティング、研修・セミナーなどでお伝えしております。そのため、ここでは割愛しますが、みなさまの身の回りにある身近な事例などの解説を通じて、その一端はお伝えしております。よろしければ、「記事・事例のまとめ」を参照ください。
人の情報処理システムとは
(1)の視点で、更に、検討を進めた結果、そもそも、人はどのようなしくみ、システムで行為を行っているかのモデルが必要ではないかという結論に至りました。それが、人の情報処理システムです。
詳細は以下の動画を参照頂きたいですが、要するに、人の行為を機能、働きという視点で、詳細に見たら、「記憶」「認知」「判断」「行動」の4つに分けられる、ということです。
ヒューマンエラーのタイプとは
エラーのタイプに関しても、詳細は、上の動画を見て頂きたいですが、人の情報処理システムから見ると、人の行為は「記憶」「認知」「判断」「行動」の4つの機能から構成されており、エラーはその機能がうまく働かなかった状態と考えると、「記憶エラー」「認知エラー」「判断エラー」「行動エラー」の4つがあるということになります。
ただし、当ラボでは、決まり事を守らない違反なども、ヒューマンエラーの一つととらえておりますので、「あえて型エラー」というタイプも設定しています。
先ほど挙げた、エラーの2分類、3分類との関係を整理すると、以下のようになります(あえて型エラーは除く)。あくまでも、書籍を読んだ限りでの当ラボの見解であることをご容赦ください。
| 分類 | エラータイプ | 記憶エラー | 認知エラー | 判断エラー | 行動エラー |
| 2分類 | コミッションエラー | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2分類 | オミッションエラー | 〇 | |||
| 3分類 | スリップ | 〇 | |||
| 3分類 | ラプス | 〇 | |||
| 3分類 | ミステイク | 〇 |
ヒューマンエラータイプを活用したエラーリスクの抽出
先ほど、「(1)ヒューマンエラーの未然防止につながる切り口、視点が必要である。」に関して、エラーリスクの切り口、視点として、エラータイプがそれにあたると述べました。それに関して、言及しておきたいと思います。
お客様との打ち合わせメモから見積書を作成する作業で考えてみましょう。見積書はシステムに必要な情報を入力すればできるとし、大まかな流れは以下です。
①打ち合わせメモを見る。
②見積書作成システムの必要な箇所に、必要な情報を入れる。
③入力内容を確認する。
④見積書を発行するために、システムの「見積書発行ボタン」を押す。
例えば、①は「認知」しているので、打ち合わせメモの見間違い、認識間違いなどのリスクが考えられます。
②に関しては、商品名を入力するとしましょう。商品名は、そのまま直接入力する形式(選択肢や入力候補が出てきて、選択して入力するタイプではない)だとすると、入力する際に、システムの商品名入力欄を見ると思いますので、その欄の見間違いや入力キーの表示の見間違いなどの認知エラーや入力キーのタッチ間違いなどの行動エラーが考えられます。
③は確認のために、システムへの入力内容を見ますので、その見間違いである認知エラーが考えられます。
④は「見積書発行ボタン」を探すために見ると思いますので、その見間違いである認知エラーや頭では、「見積書発行ボタン」を押すつもりが、つい、となりの別のボタンをクリックしてしまう行動エラーが考えられます。
このように、エラーリスク抽出の対象となる作業・業務の方法・手順や動作を、人の情報処理システムの視点に照らし合わせ、それらがどの機能に当たるかを考え、それらが機能しないエラーをリスクとして抽出していけばよいことになります。
このような切り口、視点があれば、事故やトラブルが発生していなくても、作業・業務を現場で実際に観察したり、現場で観察せず、作業標準書、手順書を見て、イメージしながらでもエラーリスクを抽出できると、当ラボでは考えておりますが、いかがでしょうか。